- 「これまでリファラルで採用を進めてきたけれどちょっと限界がきたな・・・。」
- 「そろそろ本格的に採用をはじめたいけれど、何からはじめたら良いですか?」
そのようなご相談をいただくことも増えてきました。
スタートアップの採用は、企業の成長を左右する重要なプロセスです。しかし、大手企業とは異なり、スタートアップには特有の課題と注意点があります。
本記事では、採用活動を始める前に知っておくべき重要なポイントを解説します。
求人広告の費用・特徴がまるッとわかる!
今だけ中途求人媒体 比較表の資料を無料配布中!
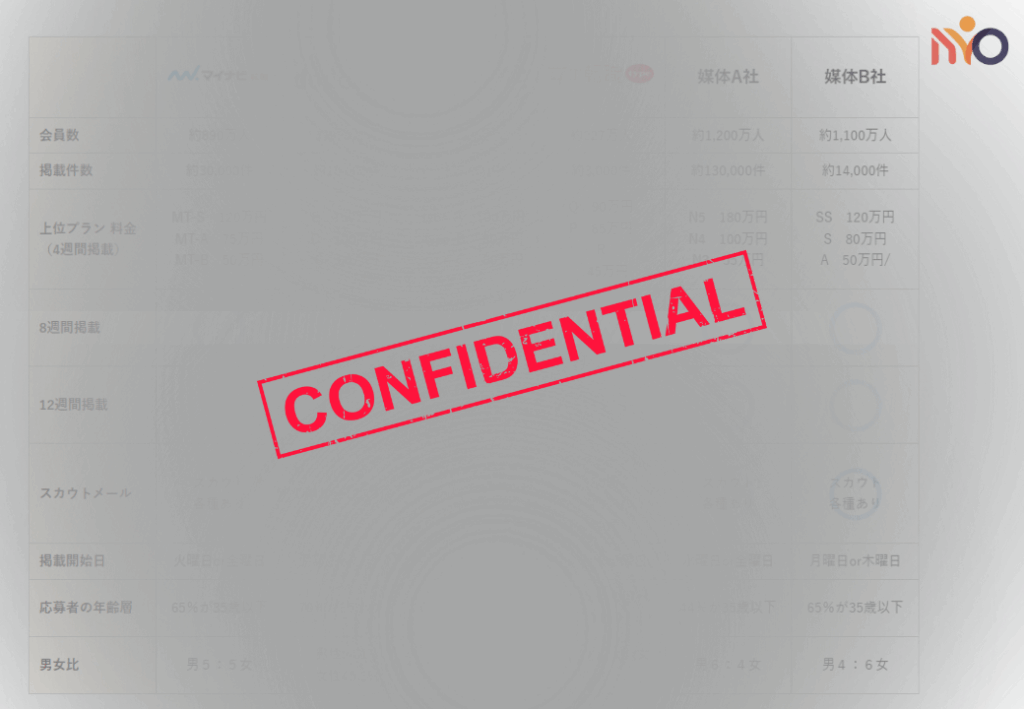
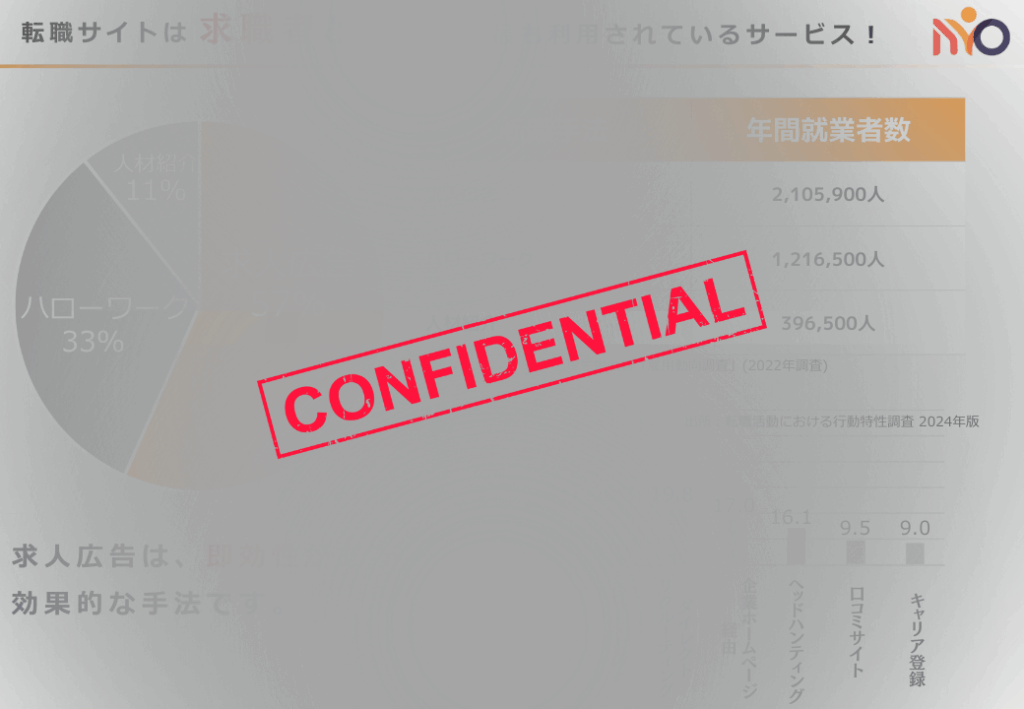
\毎月5社限定無料ダウンロード!/
求人広告の費用・特徴がまるッとわかる!
今だけ中途媒体を比較した資料を無料配布中!

\毎月5社限定無料ダウンロード!/
スタートアップの採用が難しい理由3選

スタートアップの採用は難しい理由は大きく分けて3つあります。
- 即戦力の人材獲得は難易度が高い
- 採用担当者が不在で経営陣がやらなければならない
- 待遇や労働時間の社内規定の整備が不十分
即戦力の人材獲得は難易度が高い
スタートアップは事業フェーズの特性上、すぐに成果を出せる即戦力となる人材を求めています。しかし、市場全体で見ても、特定のスキルや経験を持つ即戦力人材の数は限られており、獲得の難易度が高いのが現状です。
優秀な人材は複数のオファーの中から企業を選ぶため、競争に打ち勝つ必要があります。結果として、求めるスキルレベルと採用市場とのギャップに苦しむケースが多いのです。
採用担当者が不在で経営陣がやらなければならない
多くのスタートアップでは、専任の採用担当者が初期段階では不在です。そのため、採用活動は、本来事業推進に集中すべき経営陣(CEOやCTOなど)が兼任せざるを得ません。
採用業務に割ける時間が限られているため、採用戦略の立案、求人媒体の選定、候補者との面談、内定者フォローといった一連の採用フローが負担になります。
待遇や労働時間の社内規定の整備が不十分
企業としての基盤がまだ十分に固まっていないため、給与体系や評価制度、福利厚生、労働時間に関する社内規定の整備が不十分であるケースが散見されます。
特に、公平性・透明性のある評価制度がないと、候補者は自身の将来のキャリアパスや賃金に不安を感じやすくなります。候補者は、安定性や将来性も重視するため、この点の明確化は必須です。
採用ノウハウがない
立ち上げ期のスタートアップの多くは、専任の採用部門を持たず、採用に関するノウハウが社内に蓄積されていません。どのような媒体を使えば良いか、どのような質問が有効か、他社とどう差別化するかといった知識が不足していると、非効率な採用活動になります。
このノウハウ不足が、採用活動のPDCAを回すことができず失敗や時間ロスにつながります。結果として、場当たり的な採用活動になり、優秀な人材を獲得が難しくなってしまいます。
スタートアップの採用基準・求める人材3選
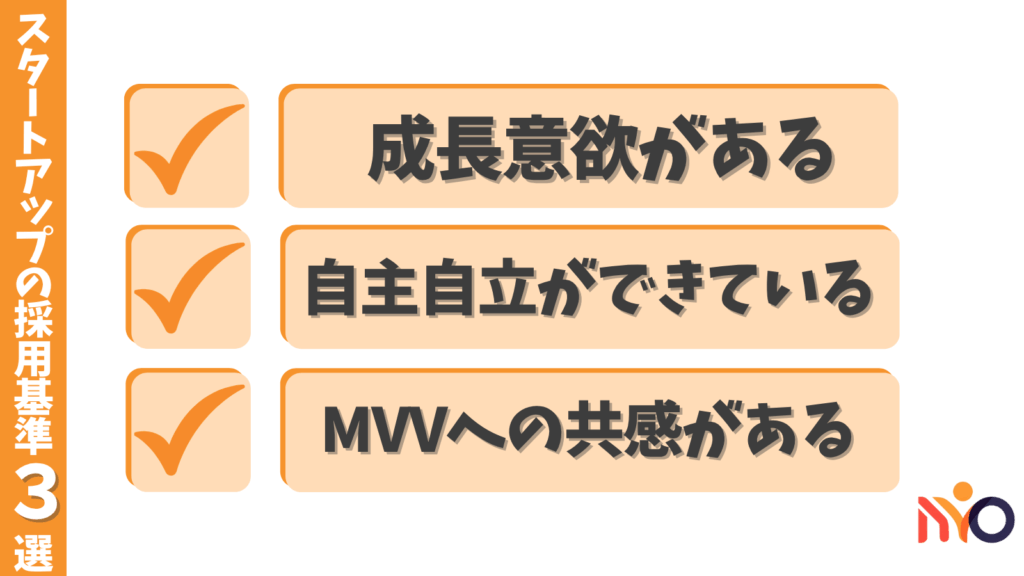
スタートアップが求める人材は、大手企業とは異なる特性を持っています。事業フェーズと環境の特殊性から、特に重要となる3つの採用基準を紹介します。
- 成長意欲がある
- 自主自立できている
- MVVへの共感がある
成長意欲がある
スタートアップの環境は変化が激しく、事業内容や役割が短期間で大きく変わることが頻繁にあります。そのため、既存のスキルに頼るだけでなく、常に新しい知識やスキルを学び続け、自己成長を追求する意欲が大切です。
困難な状況でもそれを成長の機会と捉え、ポジティブに取り組める人材こそが、事業を牽引する力となります。入社時のスキルよりも、変化に対応し、学び続けるポテンシャルを重視することが重要です。
自主自立できている
組織体制や業務フローが未整備なスタートアップでは、誰かに指示されるのを待つのではなく、自ら課題を見つけ、解決に向けて行動できる自主性・自立性が求められます。
特に、経営陣が採用を兼任している場合、細かなマネジメントが難しいため、自律的に判断し、責任をもって最後までやり遂げる力を持つ人材は、組織の核となります。
MVVへの共感がある
採用において、候補者が企業のMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)に深く共感しているかを最も重視すべきです。なぜなら、人材を引きつけ、定着させる最大の武器は「働く意義」だからです。
ミッションやビジョンに心から共感し、「この事業を成功させたい」という強い動機を持つ人材は、難しい状況に直面しても粘り強くコミットメントし続けます。
スタートアップが優秀な人材を獲得するためには、「何のために働くか」という企業の存在意義への深い共感が大切です。
スタートアップの採用の失敗する事例3選
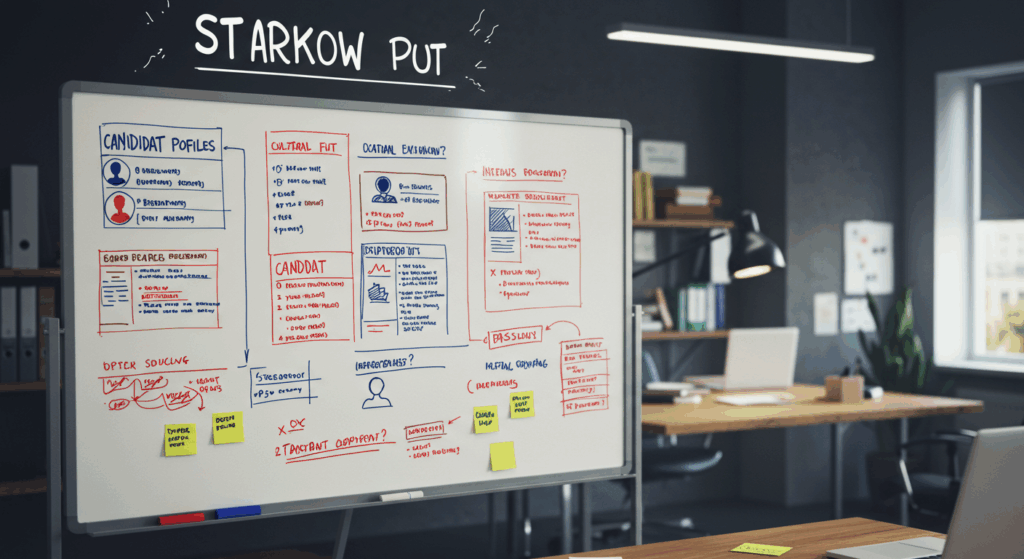
スタートアップの採用でよくある失敗事例を3つご紹介します。
- 人材採用の基準が高すぎる
- 企業の価値観や思想に合っていない
- 入社前に想定していたスキルがない
人材採用の基準が高すぎる
多くのスタートアップは、「即戦力」「高いスキル」を求めるあまり、完璧な人材像を描きがちです。しかし、すべての条件を満たす理想的な候補者は滅多にいません。
例えば、エンジニア職で特定のスキルに加えて、マネジメント経験、営業力まで求めるケースです。結果として、選考の通過者が現れず、採用期間が長期化します。
採用基準が高すぎることで、本来なら活躍できる優秀な候補者を見逃している可能性があるのです。
企業の価値観や思想に合っていない
スキルや経験が十分でも、企業の価値観に共感できない人材は、早期離職につながるリスクが高いです。スタートアップは変化が激しく、時に泥臭い仕事も多いため、企業文化とのフィット(カルチャーフィット)が重要になります。
採用時のチェックポイント
| 観点 | 失敗例 | 成功へのポイント |
| スキル | 求めるスキルは満たしている | スキルと成長意欲のバランス |
| 価値観 | 会社の考えを伝えていない | 入社後の活躍イメージを共有 |
| 思想 | 給与や待遇面のみを強調 | 理念への共感度を重視する |
面接でスキルチェックに終始せず、「なぜこの会社で働くのか」という候補者の内なる動機を深く掘り下げることが大切です。
入社前に想定していたスキルがない
採用後、「話は上手だったが、実際の業務では期待していたスキルがなかった」というミスマッチもよくある事例です。特にスタートアップでは、入社後の教育リソースが限られているため、即戦力性を過信した採用は大きな痛手になります。
この問題の原因は、採用プロセスでのスキル評価の甘さです。例えば、プログラミングスキルであれば、口頭での確認だけでなく、実技試験や過去のアウトプットの提出を必須とするなどの工夫が必要です。
採用段階で「いま何ができるのか」を正確に見極めることが、スタートアップの採用では重要です。
スタートアップの採用を成功させるポイント6選
スタートアップの採用を成功させるポイントを紹介します。優秀な人材を獲得し、事業成長を加速させるための具体的な方法を6つあります。
オウンドメディアを活用して積極的に発信
採用力を高めるには、オウンドメディアでの情報発信が大切です。なぜなら、スタートアップは知名度が低いため、求人広告だけでは企業の魅力や働く意義が伝わらないからです。
例えば、経営者の思想、開発文化、社員のインタビュー、日々の働き方などをブログやSNSで発信します。企業のリアルな姿に共感した質の高い候補者が集まりやすくなります。企業の「熱量」を伝えることで、ミスマッチのない採用を実現できます。
事業規模に合った採用活動をする
自社のステージに合った採用手法を選ぶことが重要です。資金やリソースが限られたスタートアップが、広範囲な媒体に大量の求人を出すのは非効率です。
創業初期なら「リファラル(社員紹介)」や「ダイレクトリクルーティング」など、ピンポイントで接触できる手法に注力します。
成長期に入ったら、媒体の活用や採用担当者の増員を検討するなど、常に活動の規模と企業の成長を連動させることが成功の鍵です。リソースを分散させず、効率と確実性を重視した採用戦略を立てましょう。
選考基準や求める人物像が定まっている
採用活動を始める前に、明確な選考基準と人物像を定義すべきです。基準が曖昧だと、評価がブレたり、「なんとなく良い人」で採用してしまい、入社後に期待通りの活躍が得られないことがあります。
単に「コミュニケーション能力が高い人」ではなく、「不確実性の高い状況でも、自ら課題を設定し、周囲を巻き込んで解決できる人」のように、具体的な行動特性(コンピテンシー)まで落とし込みます。
採用に関わる全員が共通認識を持つことで、ブレのない一貫した採用が可能です。
待遇面や労働環境の整備
金銭面以外の魅力も積極的に候補者に提示しましょう。待遇面だけで大手と競うのはスタートアップにとって現実的ではありません。
柔軟な働き方や自己成長を支援する環境を整備しましょう。
- ストックオプション制度
- フレックスタイム
- リモートワーク制度
- 技術書籍購入補助など
「ここで働くことで得られる価値」を高め、企業の成長と連動した魅力的な環境が、優秀な人材を引きつけます。
最初は業務委託なども視野に入れる
最初から正社員雇用にこだわらない柔軟な採用が有効です。企業と候補者双方にとってお試し期間となる意味でも業務委託やアルバイト採用など検討します。
特定のプロジェクトや限定的な業務を業務委託で依頼し、双方のカルチャーフィットやスキルレベルを測ります。相性が良ければ正社員登用を提案することで、ミスマッチのリスクを最小限に抑えた確実な採用が可能です。
段階的な関わりを持つことで、入社後の定着率と活躍度を高められます。
人材採用や求人のプロに相談する
採用の専門家であるプロの力を借りることも検討しましょう。採用戦略の策定、適切な母集団形成、面接官トレーニングなど、専門知識が必要な領域は多岐にわたり、内製化が難しいためです。
採用代行(RPO)や、スタートアップに特化したエージェントを活用することで、自社のリソースをコア業務に集中させつつ、採用の質とスピードを上げられます。外部の知見を有効活用し、採用活動を迅速に進めましょう。
スタートアップ採用におすすめの採用手法5選
スタートアップ採用におすすめの採用手法5選を紹介します。
- 企業の採用ホームページ・SNS経由での情報発信
- 人材紹介エージェント
- ダイレクトリクルーティング(スカウト)
- リファラル採用(社員紹介)
- 業務委託(外部プロフェッショナル)の活用
企業の採用ホームページ・SNS経由での情報発信
企業の採用ホームページやSNSは「熱量」と「未来」を直接伝える最もコストパフォーマンスの高い方法です。
特にオウンドメディアやSNSは、スタートアップの思想や文化(カルチャー)を深く理解してもらいやすく、採用活動の初期段階から、情報発信に注力すべきでしょう。
求人媒体では伝えきれない、働く環境や社員が、ミッション、ビジョン、バリューを語ることで企業の価値観に共感した候補者からの応募が増え、入社後のミスマッチを防ぐことにつながります。
人材紹介エージェント
即戦力人材を効率的に獲得したい場合に有効な手法です。特に特定のスキルや経験が必須となるポジションの採用でおすすめです。
エージェントは自社のリソースを使わずに、要件に合った候補者をスクリーニングしてくれます。ただし、成功報酬型が多いため、採用時のコストは高めです。
スタートアップに特化したエージェントを選べば、業界への理解が深く、マッチ度の高い人材に出会える可能性が高まります。
ダイレクトリクルーティング(スカウト)
企業が候補者に直接アプローチする能動的な採用手法です。スタートアップにとって最も重要な「欲しい人材にピンポイントで接触できる」メリットがあります。
プラットフォームへの登録やスカウト文の作成にはリソースが必要ですが、長期的に見れば採用単価を抑えることができます。特にニッチな技術を持つエンジニアや、経験豊富なマネージャー候補の採用に効果的です。
リファラル採用(社員紹介)
最も信頼性が高く、定着率も高いとされる採用手法です。社員の友人・知人を紹介してもらう仕組みで、企業文化や仕事内容を深く理解した上での応募となるため、ミスマッチが少ないのが特徴です。
社内のコミュニケーションを活性化し、報酬制度やインセンティブを設定するなど、「リクルーター制度」の仕組み化が重要です。コストを抑えつつ、質の高い人材を継続的に採用できるため、スタートアップにとって必須の採用手段です。
業務委託(外部プロフェッショナル)の活用
正式な採用ではないものの、特定の課題を迅速に解決したいスタートアップにとっては有力な選択肢です。特に初期段階では、正社員として採用することが難しいハイレベルな専門家と、業務委託契約で組むことができます。
業務委託を視野に入れるべきケース
| 採用ポジション | 特徴 |
| CMO/CFO | 高度な専門性と経験が必要 |
| 新規事業立ち上げ | スピードと即戦力性が求められる |
| 特定技術のエキスパート | 正社員として市場に少ない人材 |
業務委託だと「お試し期間」として将来的に正社員としての採用を打診できる可能性も生まれます。柔軟な視点を持つことが、スタートアップの採用を成功に導きます。
まとめ |スタートアップの採用が難しい理由とは?
スタートアップの採用が難しい最大の理由は、「ブランド力」と「リソース」の不足です。大手企業のような知名度や豊富な予算がないため、ただ待っているだけでは優秀な人材は集まりません。
成功の鍵は、「自社の魅力を能動的に発信すること」、そして「事業フェーズに合った手法を組み合わせること」です。本記事で紹介した5つの手法を戦略的に組み合わせ、難しい採用を成功へと導きましょう。
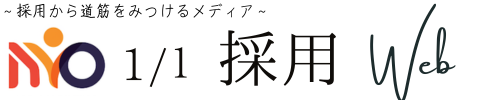


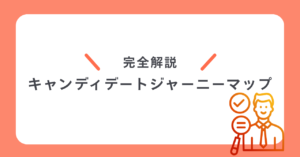

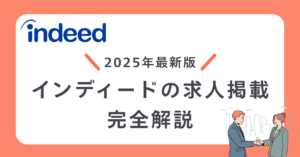
は採用後は、費用はかかるの?-300x157.png)
無料掲載できないのはなぜ?-300x157.png)
掲載終了したあとも再掲載できる?-300x157.png)
貴社の求人はまだインディードに掲載されていませんとは?-300x157.png)