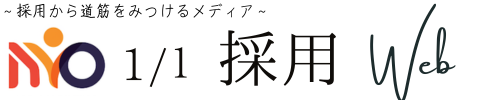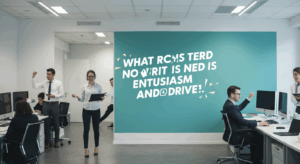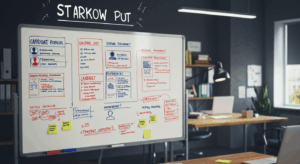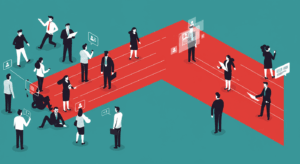人事・採用担当者の皆さん、こんな悩みはありませんか?
「いくら求人広告にコストをかけても、なかなか応募が集まらない」「やっと採用できたと思ったら、すぐに辞めてしまう」。その原因は、もしかすると採用活動の「費用対効果」が見えていないからかもしれません。求人難の時代だからこそ、単に人を集めるだけでなく、コストをかけた分以上の成果を出す戦略が不可欠です。この記事では、あなたの会社の採用活動を劇的に変えるヒントをお届けします。
採用担当者は費用対効果を意識せよ!求人難の時代に勝つための採用戦略
「採用経費がいくらかかっているか、すぐに答えられる採用担当者は意外と少ない。」この言葉に、ハッとさせられる人事担当者もいるのではないでしょうか。求人難の時代だからこそ、単に人を集めるだけでなく、採用経費の費用対効果を最大限に高めることが、企業の未来を左右します。
採用担当者は「経費」と「効率」を常に意識しよう
一人当たりの採用経費を把握している採用担当者が少ないのが現状です。さらに、自社の平均勤続年数を正確に答えられる人は、もっと少ないかもしれません。人事関係の情報は秘匿性が高いとはいえ、数百万円をかけた求人広告で採用した人材が、実績を残さずに早期に退職してしまう現実を誰も問題視しないようでは、その企業はいずれ衰退してしまうでしょう。
求人難の時代だからこそ、採用担当者には、求職者の心理を考えた求人広告を打ち出し、場合によっては社内体制を変えるほどの強い意気込みが求められます。単に人を集めるだけでなく、その人が定着し、会社に貢献できる環境を整えるまでが、採用担当者の重要な役割です。
採用担当者が、採用にかかる経費と、採用した人材がもたらす効果を常に意識し、PDCAサイクルを回すことが、企業を成長させる鍵となります。
採用担当者の役割は「採用」で終わらない
採用担当者の中には、「経営者が頑固で体制を変えられない」と嘆いている人がいます。しかし、本当に真剣に「人の大切さ」を理解しているのか疑問に感じてしまいます。なぜなら、社員が定着しない企業には、必ずどこかに問題があるからです。
新入社員は、企業に貢献したいという熱い思いで入社してきます。それなのに、社内体制や先輩社員の実態を見て「この会社では長く働けない」と思われてしまっては、いくら求人広告費をかけても、社員が定着せず、期待する費用対効果は得られません。採用担当者の仕事は、人材を採用したら終わりではありません。経費をかけて採用した人材が、その経費以上の仕事をした時点で初めて、採用担当者の仕事が評価されるのです。
真に優秀な人材を獲得し、定着させるためには、採用担当者が経営者や現場と連携し、より良い職場環境を築いていくことが求められます。
採用手法を見直し、費用対効果を最大化する
今まで行ってきた求人方法を、ぜひこの機会に見直してみてください。インターネットの普及により、求人のあり方は大きく変わってきています。求人広告が悪いわけではありませんが、それにだけに頼っていては、今の時代に合った優秀な人材を確保することは難しいでしょう。
採用手法の多様化
従来の求人広告や人材紹介に加え、企業が候補者に直接アプローチするダイレクトリクルーティングや、社員・OB/OGからの紹介によるリファラル採用・アルムナイ採用が本格化しています。また、正社員だけでなく、副業や業務委託といった多様な雇用形態も積極的に活用されています。
デジタル・AI化の加速
- SNSと動画活用: 若年層へのリーチにはTikTokやInstagramが不可欠です。企業文化や社員の様子を伝える「社員の声」動画は、応募者の志望度や企業とのマッチ度を高めるのに非常に効果的です。
- AI活用と効率化: 応募者のデータ分析や自動選考を行うAIスクリーニング、パーソナライズされた広告配信など、AIが採用活動の効率化と精度向上に貢献しています。
採用担当者も実績主義であることを理解し、一人当たりの採用経費を把握しよう
採用担当者もまた、実績で評価されるべき存在です。そのためには、一人当たりの採用経費を明確にし、その費用対効果を検証することが不可欠です。
採用活動が成功したかどうかは、単に人数を確保できたかではなく、その人材がどれだけ長く定着し、どれだけの成果を生み出したかで測るべきです。採用にかかったコストと、その人材が企業にもたらす利益を常に比較し、より効率的で効果的な採用戦略を構築していきましょう。